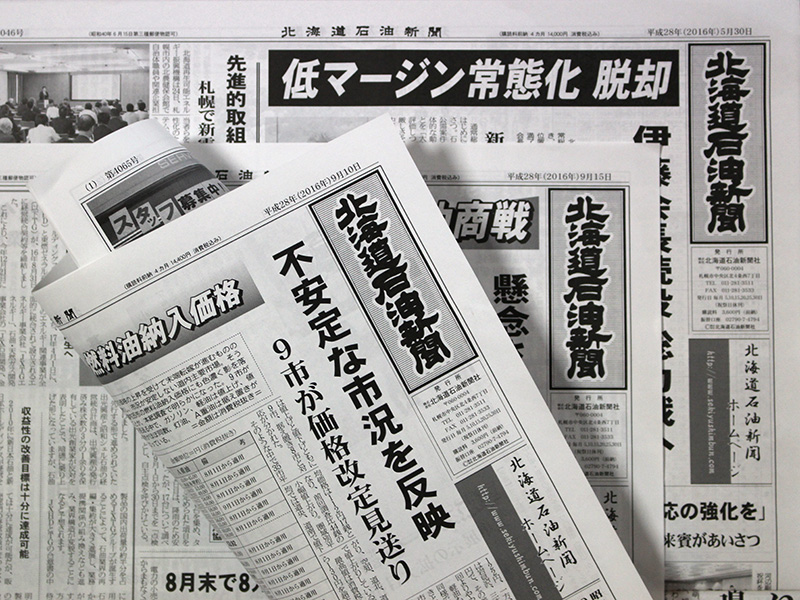
燃料油需要そのものの減退や、不毛な価格競争に伴う低マージンの常態化などから販売業者の経営は疲弊の一途。厳しさにも一層の拍車がかかる中で、今、業界を揺るがしかねない新たな問題が浮上している。微小粒子状物質(PM2・5)の一因ともされるVOC(揮発性有機化合物)対策の強化に向けた動きがそれだ。ガソリンの給油時などに発生するベーパーの回収がSSに義務付けられることになれば多額の設備投資が必要となり、経年地下タンクに続く「第2の規制強化」となるのは必至。全石連では車両搭載型装置による回収を環境省に要望するなどしているが、本道でもそれに合わせた総力の結集が不可避だ。
この問題は、中央環境審議会が平成14年4月の第5次答申で「給油所の燃料蒸発ガス対策」を指摘し「欧米での状況も踏まえ、早急に結論を出すことが適当」などとしたのが発端。その後、様々な論議が進む中で27年2月、中環審大気・騒音振動部会微小粒子状物質等専門委員会が「燃料販売業界においては自主的取組によるVOC排出量削減が進まず、他業種ほどの低減が見られない」として、給油時、荷卸し時双方における対策を「短期的課題」と位置付けたことから、にわかに注目を集め出した。
排出量削減には、給油時におけるノズルでの回収など燃料供給側での回収と、車両搭載型装置による回収の2つの方法があり、多くの国々が国境を接していることから車両の行き来が頻繁な欧州では前者、他国の車両乗り入れがほとんどない米国では後者が中心。
ただ、1台1万円程度の負担で済む車両搭載型装置に比べ、供給側での対応には計量機の取替えなどで数百万円から1千万円程度の設備投資が必要になると言われ、仮に供給側での対応が求められることになれば、地下タンクに続く「第2の規制強化」となることは必至。燃料油需要の減退に加え、価格競争に伴う低マージンの常態化にあえぐ業界にとっては、その基盤をも揺るがしかねない大問題となる可能性を秘めている。
全石連では「中小・零細事業者が多いSS業界の経営に深刻な影響を与える」などとして、車両搭載型装置による回収を環境省に要望するなどしているが、本道においても供給者側での対応「阻止」に向けた総力の結集が不可避となってきていると言えそうだ。
北海道のガソリン価格予想
12月22日(月)から12月28日(日)まで
 価格下降
価格下降
下げ傾向続く
|
12月20日付ヘッドライン
■「GSではなくSS目指せ」 SS過疎地対策で道経産局がセミナー |
■「価格」が販売業者翻弄 今年を回顧 |
■最終消費3年連続減少 2024年度エネルギー需給実績 |
■年末年始も油外増販目指す 新規獲得に注力 道エネ三角山SS |
■環境特集 |