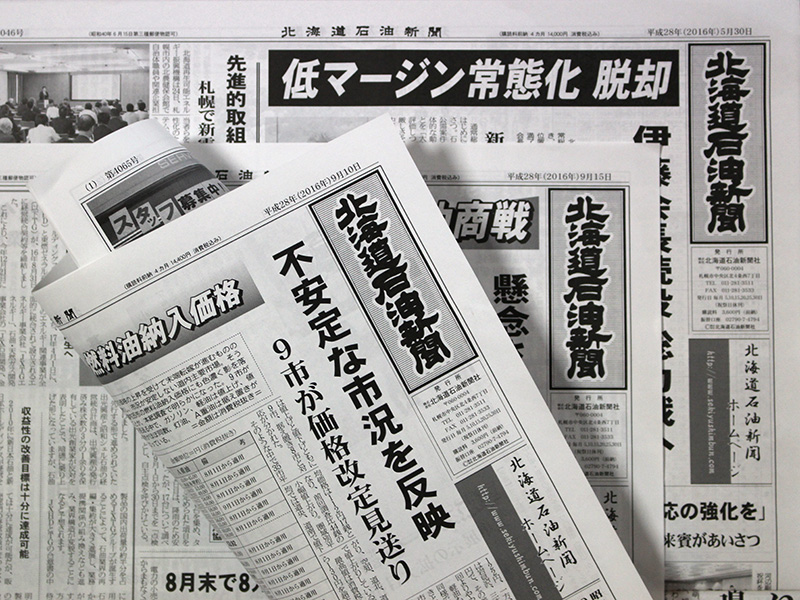
非常用自家発電機を導入するSSが道内でも急速に増加している。昨年9月の胆振東部地震、それに伴うブラックアウトの際には、自家発電機のあるSSが道内全SSの約6分の1に過ぎなかったが、今年3月末現在の住民拠点SSは震災時の約2倍に増え、9月末までには北海道の補助によるものも213カ所加わるなど、震災時の3倍近くにまで増える予定だ。
昨年9月6日未明の胆振東部地震や、それに伴い発生した道内295万世帯に及ぶブラックアウトの際、パニック買いも含め、営業するSSに長蛇の車列が発生、ところによっては大渋滞の引き金になったことはまだ記憶に新しい。
この地震が発生した時点で、国の補助を受け非常用自家発電機を導入していた住民拠点SSは236カ所。それに中核SSや小口燃料配送拠点も加え、そのうち300を超すSSが自家発電機を稼働させて営業を再開したが、道内全SSの約6分の1の稼働では需要に対応しきれず、在庫切れになるSSが続出した。
道内の住民拠点SSは2017年12月末で165カ所。それが2018年2月末には236カ所となり、さらに同年10月末で303カ所にまで増えた。そして2019年3月末には胆振東部地震発生時の約2倍、463カ所となっている。資源エネルギー庁では現在も引き続き整備を行っており、その数はさらに増えていく見込みだ。
また、北海道も胆振東部地震発生を機に昨年9月、災害時給油体制緊急整備事業費補助金としてSS195カ所への非常用自家発電機設置に向けた補正予算を編成し、国と同様、250万円を上限とする全額補助の施策を決めた。その後、エネ庁との協議などに時間が取られて4億8750万円の予算は次年度に繰り越し、今年4月1日から申請を受け付けて5月15日付で交付を決定した。
道は、国の補助が地方に多くなっていることから、都市部を優先するとともに、住民拠点SSのない町村にも配慮。上限の250万円を下回る申請もあったことから、それら差額を積み上げ、当初の計画より18カ所も多い213カ所を採択している。
こうしたものを合わせると、道が事業終了を見込む今年9月までに、非常用自家発電機があるSSは少なくとも胆振東部地震発生時の約3倍、もしくはそれ以上に増えることとなり、線引きは難しいが、ほぼ万全な体制が整うことになる。
北海道のガソリン価格予想
9月15日(月)から9月21日(日)まで
 価格上昇
価格上昇
値戻し
|
09月20日付ヘッドライン
■法令順守などで白熱議論 道北5石協「連絡会議」開く |
■発災時の「動き」再確認 清水で災害時対応実地訓練 |
■LPガスの需要拡大好機 伊藤敏憲氏ら講演 エネクス経営者セミナー |
■ローリー44台一斉点検 札幌中央消防署など4機関合同 |
■「削減目標」など俎上に 推進計画見直しで道環境審温対部会 |