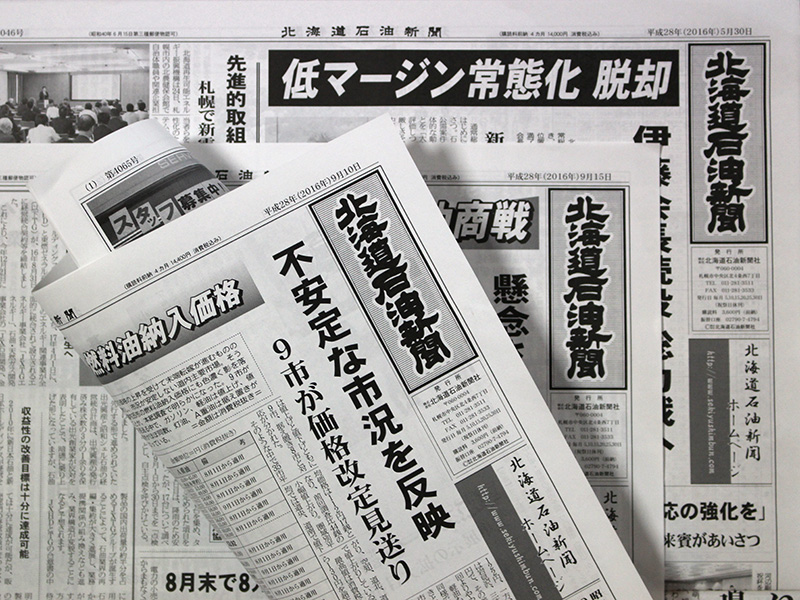
菅義偉首相の2050年までの温室効果ガス排出ゼロ表明など脱炭素社会構築に向けた機運が高まるが、本道では再生エネルギー活用の可能性が高い半面、電力の調整能力不足などが指摘されている。そうした中で国土交通省は20日、北海道水素地域づくりプラットフォーム(座長・佐伯浩北大名誉教授)の本年度会合をオンライン方式で開催し、講演などを通して水素利用の将来展望や地域マイクログリッドの有用性などを考えた。
北海道水素地域づくりプラットフォームは「北海道に豊富に賦存する再生可能エネルギーの活用を、水素を利用することにより促進させ、水素を活用した地域づくりを検討するとともに、水素の製造・利用に係る事業の振興を通じて地域に貢献していく」ことを目的に行政機関や関係団体、企業などが参加し平成27年5月に発足。これまで10回の会合を持ち、意見交換などに加え先進地視察なども進めている。
この日の会合では、主催者を代表し国土交通省北海道局の石塚宗司参事官、佐伯座長があいさつしたのに続き、東北大学大学院工学研究科電気エネルギーシステム専攻の津田理教授が「電力・水素複合エネルギー貯蔵システムについて」と題し基調講演した。
中で津田教授は、東日本大震災時の長時間停電により各所で燃料不足が発生したことから、長時間の運転に最適なエネルギー貯蔵装置として「電力貯蔵装置と水素貯蔵システムの融合」を挙げた上で「融合によりそれぞれの長所を活かし個々の短所を補完できる」と説明。再生可能エネルギー出力を高精度に変動補償するだけではなく、余剰電力でCO2フリーの水素を製造し、非常用電源にも活用できる複合エネルギー貯蔵システムの特徴などを解説した。
さらに仙台市茂庭浄水場での実証試験内容や結果なども紹介し、同システムの有用性も示した。
会合ではこのあと2氏が講演し、このうち大樹町企画商工課の伊勢厳則課長が「木質バイオマスと太陽光発電等を活用したスマート街区構築事業」について説明。さらに豊田通商が水素バリューチェーン、北海道電力総合研究所が再生エネルギー電力の有効活用技術の取り組みを紹介した。
北海道のガソリン価格予想
7月28日(月)から8月3日(日)まで
 価格上昇
価格上昇
上昇のあと、徐々に下げ方向で
|
08月05日付ヘッドライン
■令和6年度末道内SS数1641カ所に 29年連続、前年比27カ所減 |
■「随契に特段の配慮を」官公需で帯広石協が十勝振興局に要望 |
■「最賃の引き上げ必要」道最賃審専門部会が参考人の意見聴取 |
■災害時対応実地訓練始まる 給油再開への手順確認 上士幌で |
■盛況のうちに夏祭り サクライオイルショップ清田SS |