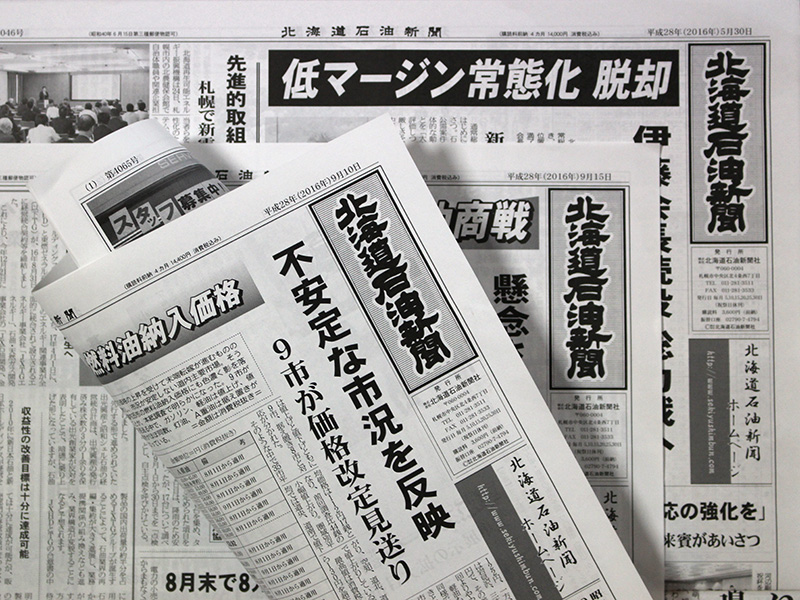
資源エネルギー庁はこのほど、揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づき令和3年度に実施した立入検査の実施状況などを取りまとめ公表した。昨年度、品確法で定める規格に適合しない揮発油などをSSで販売していた事例は230件。それらも含めて86件の立入検査を実施し、6割近い50件に品質不適合など「指摘事項」があったという。
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)中に発生した事故や全国石油協会を通じて行っている試買調査などによって判明した品確法不適合事例は、前年度より39件少ない230件。ここ10年ほどでは、平成28年度の405件をピークとして漸減傾向にある。
これら不適合事例については、過去に問題があったものも含めて資源エネルギー庁、各地方経済産業局が立入検査などを実施し「適正な品質の揮発油などの販売に関する指導」を行っている。コロナ禍で例年より数を減らしたが、令和3年度にも前年度と同じ86件の立入検査を実施した。
その結果、6割近い50件に揮発油などの品質不適合や未分析といったもののほか、登録や届け出内容の不備、分析帳簿など書類管理や店頭表示の不備など「指摘事項」があったという。
なお、エネ庁ではこれに併せ、消費者などに影響を与える恐れが高い事例として「ガソリンへの軽油混入」2事例と「ガソリンの地下水への漏えい」事例の原因や発生後の対応などを示し、一層の品質管理の徹底を求めている。
最初の「ガソリンへの軽油混入」事例は、運送会社作業員の荷卸し時の不適切な作業、SSスタッフの立ち会い不備が原因となったもので、発生後、販売を停止し消防への通報、店頭での告知を実施。混油抜き取り、タンク洗浄、油入替えとともに、作業マニュアルの改善など再発防止策も策定した。
エネ庁では「ほかにも荷卸し時に不適切な作業を行ったことで混入事故が発生している。適切な立ち会いやホース接続など作業時の確認の徹底が重要」だとしている。
もう一方の「ガソリンへの軽油混入」事例はミニローリーに積載されていた軽油をタンクに戻す際、誤ってハイオクガソリンのタンクに混入したというもので、発生後は前者と同様、販売を停止し消防への通報、ホームページや店頭での告知のほか購入者への連絡を実施。混油抜き取り、タンク洗浄、油入替えとともに再発防止策も策定しており、エネ庁では「タンクに戻す際の油種の確認が重要」だとしている。
「ガソリンの地下水への漏えい」事例は、配管の腐食により腐食孔が発生し、ガソリンが土壌に漏えいしたもので、発生後、販売を停止し消防に通報するとともに関係機関と連携し対応。在庫の抜取り、配管の交換、土壌調査後の汚染土壌の撤去に加え、営業再開後もボーリングによる土壌調査や原因究明、再発防止策の策定を進めた。
エネ庁では「在庫の不自然な減少などがないか日々の確認が重要」だとし、不自然な減少があった場合には速やかな調査を求めている。