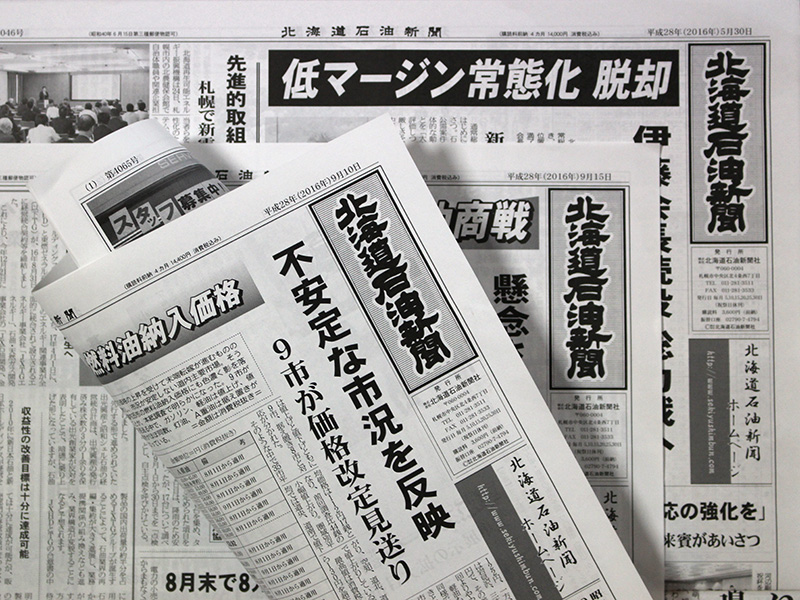
資源エネルギー庁はこのほど、揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)に基づき令和4年度に実施した立入検査の実施状況などを取りまとめ公表した。昨年度、品確法で定める規格に適合しない揮発油などをSSで販売していた事例は223件で、それらを含む111件の立入検査を実施し適正な品質での販売を指導。その際、6割を超す71件に登録内容の表示義務違反など何かしらの「指摘事項」があったという。
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)中に発生した事故や全国石油協会を通して行っている試売調査などによって判明した品確法不適合事例は、前年度より7件少ない223件。ここ10年ほどでは平成28年度の405件をピークに漸減傾向で推移している。
これら不適合事案については、過去に問題があったものも含めて資源エネルギー庁、各地方経済産業局が立入検査などを実施し、ヒアリングも行いながら「適正な品質の揮発油などの販売」に関する指導を行ってきている。昨年度は、コロナ禍の影響で例年より数を減らした前年度の86件を大きく上回る111件の立入検査を行った。
立入検査ではまた、6割を超す71件に、揮発油などの品質不適合や未分析といったものに加え登録内容の表示義務違反など、何かしらの「指摘事項」があったという。
なお、資源エネルギー庁ではこれに併せ、揮発油販売業者における一層の品質管理の徹底に向けた参考事例として「軽油地下タンクへの灯油の混入」など3事例を提示している。
荷卸し時のローリー乗務員の誤操作により発生したという「軽油地下タンクへの灯油の混入」については、発生後、原因の究明や再発防止策の策定、タンク内在庫の処分やタンク洗浄、運送会社とSSでの再発防止教育などを行っているが、資源エネルギー庁では「ほかにも荷卸し時に不適切な作業を行ったことで混入事故が起きている。SS担当者、ローリー乗務員の双方が立ち会うのはもちろん、不適切事案発生の際には情報の共有が重要」だとしている。
また、不適切な荷卸し作業によって揮発油が灯油に混入したという「灯油引火点の不適合」については、発生後、販売を停止し地元消防に連絡した上で、店頭告知、発生原因の分析、再発防止策の策定などを行っているが、資源エネルギー庁では「灯油の引火点不適合は予期せぬ発火事故につながりかねないため、荷卸し時はもとより、残油をタンクに戻す際にも油種確認が重要」と指摘。
まとまった降雨でローリー内部に浸水、そのローリーで油槽所からSSに軽油を荷卸ししたためSSタンクにも水分が混入したという「軽油への水分混入」については発生後、販売停止、地元消防への連絡、関係機関と連携しての対応、不具合のあった車両からの軽油回収、ローリー保管場所の改善、全タンクの定期的な検水徹底などを行ったが、資源エネルギー庁では「降雨時には特に水の混入に注意が必要」だとしている。