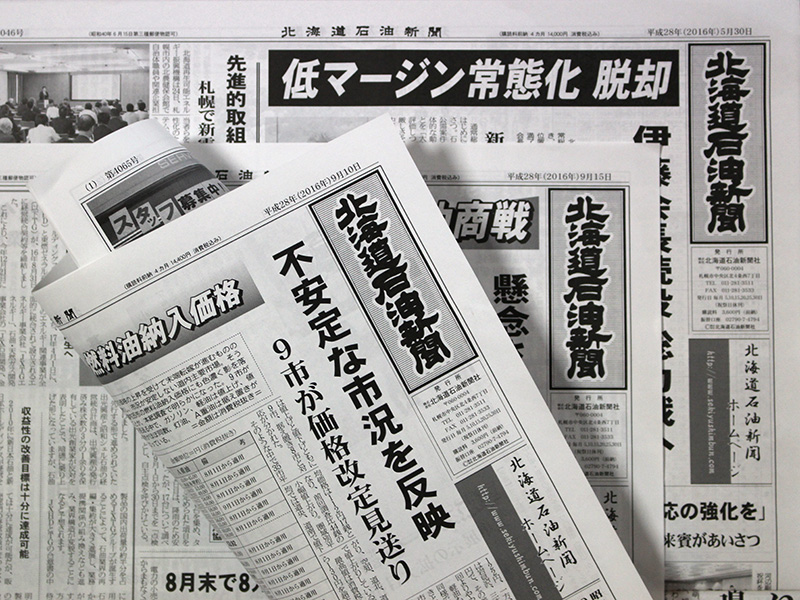
2023事業年度に営業利益ベースで「赤字」だとした企業の割合が一気に上昇、42・1%となるなど、相当数の企業が依然として厳しい経営を強いられていることが全国石油協会の「石油製品販売業経営実態調査」で判明した。調査ではまた、粗利率がわずかながら上昇する一方で、後継者不足などを理由に廃業や規模の縮小を計画している企業が15・8%となっていることも明らかになっている。以下、報告書から調査結果を紹介する。
■ 販売・財務
1企業当たりの年間総販売数量(直売・卸売含む)は自動車潤滑油10klを含めて5598kl。レギュラー、自動車潤滑油を除いてはいずれも前年度を下回り、総量で808klの減。大幅増となった前年度の反動でA重油の減少が特に際立った。
年間総売上高も、販売数量の減少などから潤滑油や油外を含め前年度比6・8%、5561万3千円の減となる7億6111万7千円。ハイオクやレギュラー、油外が前年度を上回る一方で、軽油、灯油、A重油、潤滑油は前年度を下回った。
年間総粗利額は9830万7千円で、前年度比5・2%、538万7千円の減となったが、粗利率(総売上高に占める割合)は前年度を0・2ポイント上回って12・9%となった。
また、1SS当たり月間店頭販売数量はガソリン99・5kl、軽油34・4kl、灯油17・2kl、A重油3・7klなど合わせて平均154・9kl。月間店頭売上高はガソリン1513万7千円、軽油452万1千円、灯油176万8千円、A重油35万6千円、油外168万6千円など合わせて前年度比5・2%増の2361万4千円だった。
平均粗利単価(マージン)は、レギュラーがフル19円80銭、セルフ15円20銭、軽油がフル22円、セルフ18円30銭、灯油がフル20円50銭、セルフ16円90銭などとなり、すべての油種でフルがセルフを上回った。
なお、油外の月間粗利額は平均93万4千円となっており、それに占める割合はTBASP44・6%、洗車33・9%、点検整備21・5%。
他方、営業利益ベースで「赤字」だったとした企業は、前年度を5・0ポイント上回って42・1%、また、経常利益ベースでも2・5ポイント上回って23・6%となっており、専業が兼業より赤字企業の割合が高い。
営業利益ベースで赤字とした企業のうち62・5%は赤字額が500万円に満たないが、14・9%は500万円以上1000万円未満、8・7%は1000万円以上1500万円未満、13・9%は1500万円以上。
一方で「黒字」だとした企業も、その46・9%は黒字額が500万円未満で、赤字企業と合わせると69・2%となり、依然として相当数の企業が厳しい経営を強いられていることが分かる。
運営するSS数別にみると、1カ所運営企業の45・4%、2~3カ所運営企業の40・3%、4~5カ所運営企業の37・1%、6~9カ所運営企業の13・2%、10カ所以上運営企業の16・0%が赤字だとしている。
■ 労務状況
1SS当たりの従業員数は、前年度を0・4人下回る5・9人。役員や店主が0・7人、正社員が2・8人、派遣社員や契約社員、パート・アルバイト(8時間労働換算、2時間労働×4人=1人)が2・4人となり、正社員と派遣社員などがともに前年度より0・2人減っている。
また、ガソリンの月間店頭販売量別の1SS当たり従業員数は、200kl以上が7・1人で最も多く、それに100kl以上125kl未満の6・4人、150kl以上200kl未満の6・1人、125kl以上150kl未満の6・0人、75kl以上100kl未満の5・9人などが続く。このほか25kl未満が前年度を0・3人下回って3・4人、25kl以上50kl未満が0・2人上回って4・8人となっており、販売量が多い企業の方が従業員数も多い傾向は従前と同じ。業態別ではセルフ7・0人、フル5・7人だった。
平均年収は、所長クラス(平均年齢53・1歳)が465万2千円、一般社員(同46・6歳)が346万8千円。小幅ながらともに前年度を上回っており、運営SS数の多い企業の方が高い。
また、人手不足が懸案となっている中で、SS運営に必要な人員の確保については回答した1732社の48・8%となる846社が全SSで確保できているとし、22・7%の394社が一部SSで不足、26・0%の450社が全SSで不足していると回答。
さらに2~3年後のSS運営に必要な人員確保の見通しについて、全SSで確保できると思うとしたのは21・6%の374社にとどまり、先行きへの不安も。不足している具体的な人員層(複数回答)については、マネージャー以外の正社員としたのが69・9%で最も多かった。
また、人手不足の解消に向けこれまでに行った取り組み(複数回答)は休業日の設定が32・3%で最多。それに勤務時間の短縮、雇用延長が20%台後半で続き、いずれも10%未満ながらSSの集約、セルフ化、兼業部門からの配置転換といったものもあった。
■ 異業種進出等
異業種への進出・転換を計画しているとした企業は、回答した1792社の12・3%となる221社。計画している最も有力な異業種事業(単一回答)は、中古車を含む自動車販売が35社で最も多く、それに駐車場などを含めた不動産賃貸・売買・管理が34社、レンタカーが20社で続く。前年度最多だったコインランドリーは19社で、そのほか飲食業の18社、カーコーティングの13社が2桁となっている。
さらにいずれも1桁ながらコイン洗車場、自動車整備、コンビニやスーパーなどの食品・雑貨販売、介護やデイサービス事業など福祉、車体板金塗装、農林水産業・農林漁業資材販売、土木・建設業・建設資材販売、車検、太陽光発電といったものなどもあった。
これら業種を選択した理由(複数回答)については、47・1%となる104社が「ガソリンスタンド事業との関係性が高い」ことを挙げ、さらに72社が「ガソリンスタンド事業よりも収益が見込める」こと、39社が「リスクが少ない」ことを挙げている。
■ 経営上の課題
今後のSS経営の方針について、回答した1853社の70・8%、1311社は「継続する」とし、規模の拡大もわずかながらあったが、その一方で「廃業」を考えている企業が9・0%、167社、規模を縮小する企業が6・7%、125社あり、未定だとする企業も11・2%、207社に及んだ。
廃業を考える理由(複数回答)については、前年度と同様、後継者の不在が52・1%、87社で最も多く、施設の老朽化が42・5%、71社でそれに続く状況。加えて燃料油販売量の減少や粗利の減少、地下タンク規制強化への対応不能といったものも依然として多く、さらには従業員の確保が困難、運転資金が不足、油外収益が減少、仕入れ先の取引条件改善が困難といったものもあった。
廃業の時期は59・9%の100社が「具体的には未定」だとしたが、13社が1年以内、16社が3年以内、34社が5年以内としている。
■ その他
災害対策として、すでにSSで導入している設備(複数回答)で最も多かったのは、回答した1667社の77・0%となる1283社の自家発電機。以下、井戸設備、緊急用可搬式ポンプ、情報通信機器、貯水設備などが続く。
今後の導入を検討している設備については「ない」が57・5%を占めたが、最も多かったのは情報通信機器、次いで緊急用可搬式ポンプだった。