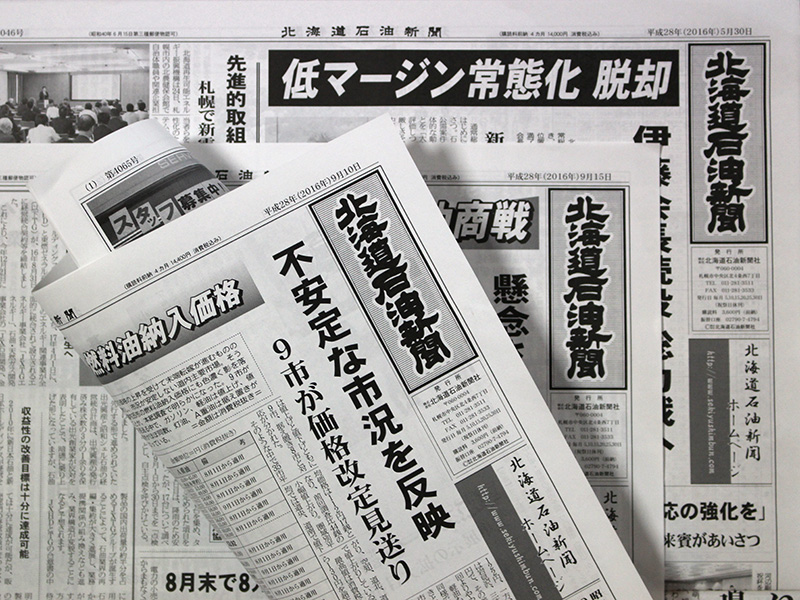
エネルギーの自由化に伴い異業種からの新規参入が続く昨今、道内における住宅の暖房熱源分野でも熾烈なシェア競争が繰り広げられている。灯油が都市ガスの猛攻を受け、守り続けた「主役の座」が脅かされているのは周知の事実。住宅関係者は一様に東日本大震災を機に都市ガスが増加していると言い、拱手傍観できない状況だ。競争が激化する中で灯油の復権に向けた打開策はあるのか。戸建て住宅の暖房に関する調査結果や住宅メーカー側の分析をもとにその糸口を探る。
札幌圏で戸建て住宅を提供する主要住宅メーカー10数社および関係団体等に対し本紙は9月、住宅購入者が選択した暖房用熱源についての聞き取り調査を実施した。その結果、都市ガスが5割強と圧倒的な支持を得ていることが判明。続いて灯油が3割弱、電気が2割未満だった。
この調査内容について北海道ガス(以下、北ガス)の広報担当者は「弊社の調査データと合致する」と回答。都市ガスの攻勢がマンションだけでなく戸建て住宅にも及んでおり、灯油が守勢に追い込まれている実態が浮き彫りになった。
北海道建築指導センターによると、2005年以前は灯油暖房が主流だったが、それ以降はオール電化住宅が台頭。ところが東日本大震災で状況は一変し、都市ガスを暖房熱源とする戸建て住宅が増えつつあるという。
戸建て住宅の購入者が都市ガスを暖房熱源として選択する理由について、北ガスは「住宅メーカーへの営業的アプローチの成果」と話すが、エネルギー自由化の動きに連動させた中期経営計画がバックボーンになっているのは確かなようだ。
北ガスは、道内の都市ガス利用顧客件数約85万件のうち、その6割強に当たる約56万件を有するが、2030年代までに100万件規模まで拡張する計画を持つ。
「ガス導管網エリアを拡大するのではなく、現エリア内で導管網を拡充させる」(同社広報担当者)ことで、地下鉄駅周辺など都心部を中心に普及率を80%まで高める方針だという。
一方、LPガス業界も都市ガスの攻勢を警戒する。都市ガス導管の延伸が進めば競争が激化する可能性があるからだ。加えて、道内で約150万世帯が使っているLPガスは、主流が調理や給湯だが、その分野でも都市ガスの進境は著しい。
劣勢に甘んじている手はない。当面、都市ガスの導管供給は経済効率上、一定レベルの需要集積があるエリアに限られると考えられる。それ以外の地域は灯油やLPガスの優位性が絶対的であるから、じっくりと対策を練るべきだろう。
また、ある住宅メーカーの営業幹部は「一般に住宅は約30年サイクルで建て替えるが、最初に選択した熱源を継続する傾向にある」と話す。であれば、業界が一丸となって顧客といかに強固な信頼関係を形成するかが喫緊の課題となる。